次世代の健康も食で守る!「どどメシプロジェクト」
2025.03.17
Q1: なぜ研究室で「どどメシプロジェクト」に参加しているのですか?
佐藤先生:「大学生になるとだんだん自立していき、食生活のあり方を自分で決めていくようになると思いますが、大抵の場合、自分の身体には無頓着で不健康な生活を送りがちです。“きちんとした生活は、結婚や妊娠を迎えるころ、あるいは中年以降に実践すればよい”と考えている人も少なくないでしょう。しかし、それでは実は遅すぎるのです!男性も女性も、若い時の生活習慣は本人とその子どもたちの将来の健康に影響をおよぼしてしまいます。当基礎栄養学・ゲノム医科学研究室では、このような危機感を持って、若年成人の食生活を改善するアプローチについてさまざまな角度から日々検討しており、『どどメシプロジェクト』もその1つとしてスタッフ、大学院生、卒業研究生が一緒に取り組んでいます。」
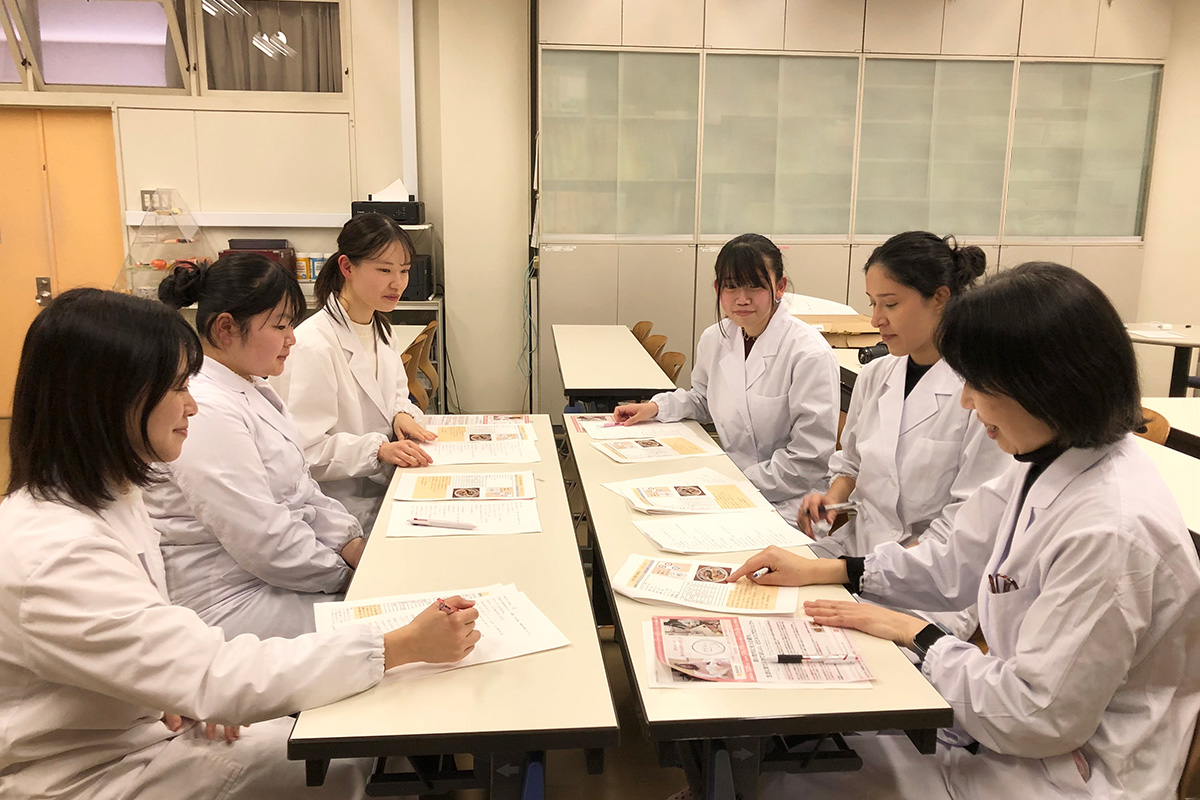
Q2: 具体的にどのような活動をされているのですか?
佐藤先生:「『どどメシプロジェクト』では、葉酸やビタミンD、カルシウム、鉄、食物繊維など、妊娠前から妊娠中に重要な栄養素を手軽に取ることのできる料理レシピ(どーはどメシのレシピ)を短い動画にして公式Instagramを通して情報発信しています。献立を考えて料理することにとどまらず、動画を編集したり、キャプションを考えたりするところも重要です。」
高橋さん:「自分でレシピを考える機会は何度もありましたが、そのレシピを自分たちで発信していく経験はあまりなかったので、とても新鮮な経験に感じています。たくさんの妊婦の方々が、元気な赤ちゃんと出会える手助けができればと思って活動に参加しています。」
佐藤先生:「どどメシのレシピは、本格的な料理を目指すのではなく、できるだけ簡単に短時間でできるものを考えています。例えば、和食を自分で作るとなると少し敷居が高いと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、今回学生さんたちが考えた『鮭のホイル焼き』『枝豆とひじきの炊き込みご飯』などは、とても簡単に作れます。」
宮澤さん:「私は、『鮭のホイル焼き』を考えました。鮭とブロッコリーをあわせ、ビタミンDや葉酸を手軽に取れるよう工夫をしました。SNSを通じて、“これは作ってみたい”と思ってもらえるように、不足しがちな栄養素を取り入れつつも美味しさ・彩り・簡便さを兼ね備えた料理になるよう工夫しました。」
久保田さん:「私は、『枝豆とひじきの炊き込みご飯』を考えました。食事全体で必要な栄養素を摂ると考えた時に、普通、主食は主に炭水化物を摂る役割になります。どどメシでは、若い人々に不足しがちな栄養素を足していきたいので、主食に、葉酸の豊富な枝豆を加え、ひじきも合わせて鉄や食物繊維をちょい足ししていくのが良いと思いました。具材を入れて炊くだけの“炊き込みご飯”は簡単ですし、いろいろとアレンジができます。その時の体調に合わせて具材のバリエーションを変えれば、上手に優先したい栄養素の補給ができると思います。」

Q3: 今、新たに挑戦しているレシピにはどんなものがありますか?
佐藤先生:「主食や副菜はもちろんスイーツにも挑戦しています。定番のチョコレートやあんこなどは、一般的には健康な食品とはいえませんが、ひと工夫して、健康度をアップすることにも挑戦してみました。チョコレートを使ったお菓子でも、野菜や豆を取り入れることによってミネラルや食物繊維を摂ることができます。また、腸活(腸内環境を整える)効果を期待してあんこを使った和風スイーツにもち麦を加えてみました。学生たちからは、“授業で学んだ日本の若い女性のやせ、エネルギー摂取不足という課題に対して、このような健康的なお菓子を広めることによって、少しでも貢献できればうれしい”という声が上がりました。」
Q4: Instagramには料理レシピだけがのっているのですか。
佐藤先生:「いいえ、Instagramには『どどメシレシピ』のほかにも、『DOHaDの考え方』『妊娠出産に準備しておくと良いこと』『関連する医学、保健学、栄養学の豆知識』なども載せています。何気なく目にしたInstagramで、役に立つ知識を自然に得ていただける点がアピールポイントです。」

Q5: 最後に、「どどメシプロジェクト」の目標を教えてください。
高橋さん 「私は昔から小児栄養に興味があり、このプロジェクトで少しでも子どもの健康に関われればと思い参加しました。自分の考えたレシピがお役にたてて、お母さんも子どもさんもずっと元気に過ごせる人が増えることを願っています。」
宮澤さん 「私は母子医療に関心を持ち、管理栄養士の勉学に励んでいます。今後、このプロジェクトを通してさらに専門性を高め、より実践的な学びを得たいと思っています。そして、この活動が必要としている方々の支えとなればうれしいです。」
久保田さん「『どどメシプロジェクト』に関わる中で、食の大切さや工夫の仕方など私も多くのことを学んでいます。作成したレシピを通じて、どなたかの食生活に少しでも役立つ情報をお届けできれば幸いです。」
佐藤先生:「このプロジェクトは、当事者の大学生や大学院生が中心となって同世代の若者に“今生活習慣に気をつけて身体を大事にすることが重要だ”ということを伝える活動です。「どどメシプロジェクト」の活動が広がることで、若い世代に向けて健康的な生活習慣の重要性が浸透し、次世代の健康を守る意識が一層深まることが期待されます。」

食物学科は、2025年4月に「食科学部」として新たな一歩を踏み出します。これからも、科学的な視点と創造力を生かし、食の未来を切り拓いていきます。
※1 DOHaDとは、Developmental Origin of Health and Diseaseの略で、生涯健康で過ごせるか、それとも病気になってしまうのか、その要因は(遺伝や成人になってからの生活習慣だけでなく)発生発達期にもある、という考え方です。歴史的には、赤ちゃんの時にお母さんが低栄養などの問題があった場合に、子宮内の発育に何らかの問題が生じ、それがもとで大人になってから病気になりやすくなることが観察されてこの概念が広く知られるようになりました。ところが、研究が進むにつれて、妊娠期だけではなく、妊娠する前のお母さん、お父さんの生活習慣や環境も胎児発育とその後の病気のなりやすさに関係することがわかってきています。
※2 プレコンセプションケアとは、「プレ」は「〜前の」、「コンセプション」は「受胎」、「ケア」は「健康管理」の意味で、成育医療等基本方針(2021年)では、「女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み」としています。つまり、子どもを授かる前から、健康状態や生活習慣を見直し改善していくことです。妊娠する前のお母さん、お父さんの健康状態や生活習慣があまり良くないと、子どもさんの将来の健康に影響が及ぶだけでなく、妊娠合併症のリスクが高まります。最近の研究から、母児の命の危険にまで及ぶこともある妊娠合併症の原因として、お父さんの健康状態や腸内環境状態の悪化も関係する可能性が注目されるようになってきました。健やかな妊娠期と子どもさんの健康のためにプレコンセプションケアは非常に重要です。













