ポリシー
ポリシー
理学部 紹介

本学の理系教育の伝統を背景に1992年、私立女子大学としては唯一の理学部が創設されました。理系女性研究者育成は我が国の緊急の課題になっていますが女子大学にこそその役割が期待されています。
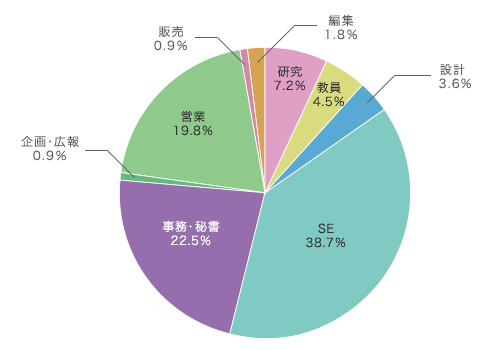
本理学部は上記2学科で構成されています。基礎学力をつけるとともに多様な領域で社会に貢献できる応用力を身につけます。

実験実習科目が多く充実した実験施設で少人数によるきめこまかな指導が行われています。卒業研究ゼミでは1人ひとり与えられた課題に取り組み4年間の大学生活の集大成として報告書にまとめます。
理学部Q&A
数物情報科学科
-
学科のポイントはなんですか?
1.数学、物理学、情報の3つの分野の科目を学ぶ
2.豊富な演習、実習、実験授業や目白祭を通じ、自ら企画し、実行し、まとめる力を養う
3.卒業研究では1年間一つのテーマを学び、追究する
4.研究を支える情報機器・実験設備が充実
5.卒業後は多くの学生が専門を生かして社会で活躍し、キャリアの充実を追求 -
他大学の理学部数学科・物理学科・情報系学科との一番の違いは何ですか?
他大学の数学科との違いは、4年次の卒業研究が必修であることです。全ての学生が4年次で1年間かけて卒業研究を行い、その成果を論文にまとめ、卒業研究発表会で発表します。これにより、学生のグループワークやプレゼンテーションの能力が高まります。また、学科の科目の中に教職志望の学生のための授業を用意し、中学や高校で数学を教える際の基盤となる知識を身に付けます。頑張ってたくさんの科目を履修すると、数学と情報の2教科の教員免許を取得することができます。さらに、数学コース希望の学生も、1年次に力学と実験が必修となっており、高校で学んだ微分積分が物理学にどのように生かされるかを学びます。また、プログラミングの基礎はもちろんのこと、情報科学理論の基礎も本格的に学び、大いに数学が活用されていることを知ります。
一般の物理学科との違いは、学年毎に実験科目が必修であることです。実験を通して物理法則を実践的に理解するだけでなく、グループワークを通してコミュニケーション能力やリーダーシップ、さらに毎回課されるレポート課題により理科系の作文能力を鍛えます。3年次の実験では、結果をグループ毎に発表としてまとめることでプレゼンテーション能力の向上も図っています。学年毎の実験により養われた実践的な問題解決力、発表やレポートでの表現力は4年生で卒業論文をまとめる際に大きな力になりますし、社会に出てからも大いに役立ちます。さらに物理学科との大きな違いは、1年次に数学・情報の必修科目があり、選択科目として数学や情報系の科目を履修し、数学的な論理力やプログラミング力を鍛えることができる点です。問題解決のために幅広い知識・能力を身につけることができます。
他大学の情報系学科との違いは、ソフトウエアとハードウエアの両面から情報科学を学べることです。また、情報科学を中心にしつつ、数学や物理の科目も選べるため、社会のさまざまな分野で求められる能力を身につけることができます。1年次から3年次まで系統的なプログラミングの実習科目が用意され、情報系の学生に求められるコンピュータの活用能力を鍛えます。また、人工知能やデータサイエンスに対応した科目を提供し、これからの社会で求められる能力を育成します。4年次全員が取り組む卒業研究では、このような学びに基づいて広い範囲から研究テーマを設定することができます。また、基本情報技術者試験やG検定などの資格取得に役立つ知識も身に付けることができます。さらにプログラミングコンテストや産学連携イベントなどの課外活動も積極的に企画し、より実践的で立体的な学びを実現しています。 -
高校では選択制なので、理系クラスでも数学Ⅰ~Ⅲ、A~B、物理基礎・物理を全員が勉強しているとは限らないと思います。数物情報科学科では1年次に数学と物理が必修と聞いていますが、授業についていけるでしょうか?
1年次の数学及び物理の科目「微分積分学」「線形代数学」「物理学概論」「物理学基礎実験」は、クラスを分け、比較的に少人数で授業を行っています。特に、「微分積分学Ⅰ」・「微分積分学Ⅱ」の授業は,高校の数学Ⅲで学ぶことを、もう一度、厳密に考えていきます。「微分積分学」と「線形代数学」のいずれの講義にも問題を解いて理解する演習の時間があり、担当教員がていねいに質問に対応しますので、課題等に真剣に取り組めば,十分に授業についていくことができます。また、「物理学概論Ⅰ」・「物理学概論Ⅱ」という科目は、高校物理の未履修者にも理解できる内容になっています。 -
本人の希望どおりコースを選択できますか?
コースは、原則として本人の希望をもとに決定されます。卒業研究の研究室は、本人の希望、各研究室で指導可能な人数、成績などを考慮して総合的に決定されます。 -
中学校・高等学校の「数学」「理科」教員免許に加えて、高等学校の「情報」教員免許が取得できるそうですが、複数を取得できますか?
取得可能な教諭第一種免許は以下の通りで、「数学」と「情報」、または「理科」と「情報」の2科目の免許を取得することもできます。2科目の免許を取得するには、たくさんの科目を履修する必要がありますが、十分に単位を修得していれば、一括申請で卒業時に2科目の免許を取得することもできます。(なお、「数学」と「理科」の組み合わせは履修が必要な科目の時間割がぶつからないような配慮をしていません。)
・数学コース:「数学」, 「情報」
・物理コース:「理科」, 「情報」
・情報コース:「情報」, 「理科」, 「数学」(「情報」とそのほかの1科目が取得可能)
「数学」は「中学&高校」または「高校のみ」、「理科」は「中学&高校」または「高校のみ」、「情報」は「高校のみ」です。「情報」の中学校の教員免許は存在しません。 -
実習・演習の授業は、1クラスどの位の人数で行われるのでしょうか?
数学コースでは、多くの専門科目にセットした形で演習をつけています。2年次以上の科目の通常の演習は1クラス20~40人です。
物理コースや情報コースの実験は1クラス10~15人でほとんどのテーマを2人1組で行っています。各実験は、担当教員1名と助手1名以上で指導して、細やかな実験教育を行っています。
情報コースの専門に関わる演習では、コンピュータは1人1台で、担当教員に加えて助手や大学院生のT.A.(教育アシスタント)をつけて、理解しながら演習できるように丁寧な指導を行っています。 -
コンピュータを使った実習の環境は充実していますか?
学内のメディアセンターには最新のパソコンシステムを備えた6つの演習室があり、どの学科の学生も利用できます。実習は1人1台のコンピュータを用いて行われ、教員と学生との間でコンピュータの交信が可能な教育システムも導入されています。在学生はセンターにID登録しますので、実習室の空いている時はいつでも使用できます。
さらに数物情報科学科には,学生が使えるコンピュータを設置した複数の演習室があります。このコンピュータは学科の学生向けに設定されているため、より高度な数値計算やプログラミング、画像処理のための環境が充実し、レポート作成や課題提出だけでなく、卒業研究や大学院の研究,学園祭の自由研究などに利用されています。
学内には無線LANが整備されていて、自分のノートパソコンからインターネット接続や大学の情報サービスを利用することができます。学内には、授業外の勉強に使えるラーニングコモンズも充実しているので、友達と相談しながらそれぞれのパソコンで課題などに取り組むこともできます。 -
研究職が希望なので大学院進学も考えています。研究職への就職状況について教えてください。
研究職の採用は大学院修士課程(博士課程前期)修了者以上を対象としている企業が多いです。このことから、研究職を希望する場合は、大学院に進学し、修了後に目指すことを勧めます。また、本学専攻修了者は、研究職の他に、総合職、技術開発職に就いています。また、学部卒でも本人の志向と能力により、技術職開発職に就いています。
このように、本学科・本専攻のほとんどの卒業生・修了生は大学や大学院での勉強や研究を生かした業種・職種に就いています。過去5年の主な進路状況は、以下の通りです。なお、括弧内の数字は、採用者数です。
過去5年の主な内定状況は、以下の通りです。なお、括弧内の数字は、採用者数です。
2022年度:
[学部卒]JR東日本(株)(2)、NEC(株)(3)、NHK、NTTコムウェア(株)(2)、NTT東日本(株)、PwCコンサルティング(合)、SMBC日興証券(株)、(株)SUBARU、SONY(株)、大日本印刷(株)(2)、凸版印刷(株)、日本アイ・ビー・エム(株)、日本オラクル(株)、(株)日立製作所、富士通(株)(2)、(株)富士通ゼネラル、三菱電機(株)(3)
[大学院修了](株)NTTドコモ、アクセンチュア(株)、セイコーウォッチ(株)、NEC(株)、(株)日立製作所、日産自動車(株)
2021年度:
[学部卒]JR東日本(株)(3)、NTTコムウェア(株)、SCSK(株)(2)、NEC(株)、アクセンチュア(株)、宇宙技術開発(株)、キヤノン(株)、ソフトバンクグループ(株)、大日本印刷(株)、東京海上日動システム(株)(2)、東京電力ホールディングス(株)、凸版印刷(株)(2)、富国生命保険(相)、富士通(株)、三菱電機(株)、(株)りそな銀行、(独)都市再生機構、厚生労働省、
[大学院修了]NTT(株)、アンリツ(株)、北海道電力(株)、リコー(株)、気象庁(2)
2020年度:
[学部卒]NHK、NTTコムウェア(株)、NTT東日本(株)、NEC(株)(5)、TIS(株)(2)、アクセンチュア(株)、アンリツ(株)、ソフトバンクグループ(株)、第一生命保険(株)、大日本印刷(株)(2)、日本アイ・ビー・エム(株)、日本銀行(株)(2)、日立製作所(株)(2)、富士通(株)(3)、三菱電機(株)、明治安田生命保険(相)、ヤマハ発動機(株)、金融庁
[大学院修了]SUBARU(株)、セコム(株)、三菱電機(株)
2019年度:
[学部卒]JR東日本(株)(2)、NEC(株)(2)、NTTコミュニケーションズ(株)、(株)NTTデータ、(株)NTTドコモ(2)、NTT東日本(株)、アクセンチュア(株)、キヤノン(株)(2)、セイコーエプソン(株)、大日本印刷(株)、凸版印刷(株)(3)、日本銀行(2)、富士通(株)、明治安田生命保険(相)、(株)村田製作所、総務省
[大学院修了] JR東日本(株)、KDDI(株)、(株)NTTドコモ、アクセンチュア(株)、東京電力ホールディングス(株)、大日本印刷(株)、三菱電機(株)
2018年度:
[学部卒]JR東日本(株)、NEC(株)、NTTコミュニケーションズ(株)、SCSK(株)(2)、キヤノン(株)、凸版印刷(株)(2)、東京電力ホールディングス(株)、(株)東芝、(株)大和総研、日本アイ・ビー・エム(株)、日本銀行(2)、(株)日立製作所、富士通(株)、本田技研工業(株)
[大学院修了]NTT西日本(株)、(株)日立製作所、三菱電機(株)、三菱自動車工業(株)(2)、三菱重工業(株)
です。 -
大学院へ進学する方は多いのですか?
毎年、20~30 %の学生が、本学大学院(理学研究科 数理・物性構造科学専攻 )をはじめ、他大学大学院に進学しています。また、修士課程(博士課程前期)修了後、博士課程(博士課程後期)に進学する学生も増えています。
過去5年の主な進学状況は、以下の通りです。なお、括弧内の数字は、採用者数です。
2022年度(計 20名):
[博士課程]日本女子大学大学院(2)
[修士課程]日本女子大学大学院(13)、お茶の水女子大学大学院、東京工業大学大学院、奈良先端科学技術大学大学院
2021年度(計 20名)
[修士課程]日本女子大学大学院(13)、埼玉大学大学院、筑波大学大学院、東京海洋大学大学院、北海道大学大学院、横浜市立大学大学院、横浜国立大学大学院(2)
2020年度(計 20名)
[修士課程]日本女子大学大学院(17)、東京大学大学院、東京都立大学大学院、横浜国立大学大学院
2019年度(計 16名)
[博士課程]日本女子大学大学院
[修士課程]日本女子大学大学院(9)、東京大学大学院、東北大学大学院、横浜国立大学大学院(2)、奈良先端科学技術大学院大学、早稲田大学大学院
2018年度(計 13名)
[修士課程]日本女子大学大学院(8)、東京大学大学院(2)、北海道大学大学院、横浜国立大学大学院(2)
です。 -
大学卒業後に教員を目指しています。教員の採用状況はどうですか?
各都道府県の教員採用は厳しい環境が続いていましたが、2002年度頃から改善の傾向が見られ、例えば東京都では数学・理科の教員採用試験に合格すれば(実際には補欠でも)、100%教員として採用されるようになりました(数学や英語は少人数教育が拡大したため)。また、中学・高校の教職免許を取得した場合でも、地域によっては、実際には小学校への採用となる場合も生じてきています。この場合、採用後の授業の実績や科目等履修生制度による単位の修得によって、小学校の教員免許を取得します。
過去5年の主な進学状況は、以下の通りです。なお、括弧内の数字は、採用者数です。
小学校の教員としては
2021年度(計 1名)
[学部卒]狭山市立富士見小学校 1名
数学の教員としては、
2022年度(計 1名)
[学部卒](学)創志学園 クラーク記念国際高等学校
2021年度(計 2名)
[学部卒]埼玉県公立中学校(2)
2020年度(計 3名)
[学部卒](学)信愛学園 浜松学芸中学校・高等学校、東京都公立中学校
[大学院修了](学)学習院 学習院中等科(非常勤講師)
2019年度(計 2名)
[学部卒] (学)安房家政学院 千葉県安房西高等学校
[大学院修了](学)杉並学院 杉並学院高等学校
2018年度(計 6名)
[学部卒](学)井之頭学園 藤村女子中学・高等学校、神奈川県公立中学校、茨城県公立中学校、
[大学院修了](学)学習院 学習院中等科、(学)高橋学園 千葉学芸高等学校、
(学)慶應義塾 慶應義塾中等部(非常勤講師)
理科の教員としては、
2022年度(計 1名)
[学部卒]非常勤講師として、埼玉県立高等学校 1名
2021年度(計 2名):
[学部卒]東京都立高等学校 1名、茨城県公立中学校 1名
2020年度(計 1名):
[大学院修了]東京都公立中学校 1名
2017年度(計 1名):
[大学院修了]東京都立高等学校 1名
が採用されました。
また、本学科は、横浜市、川崎市、相模原市、大阪府、京都府、京都市、徳島県、広島県などの公立学校教員採用選考試験の大学推薦特別選考を受けています。 -
情報処理技術としてプログラミングだけでなく、各種資格試験を在学中に受験したいと思います。大学の授業では、どのような勉強が可能か、具体的に教えてください。
学科の科目では情報処理技術者試験の対策とは謳っていませんが、プログラミング、コンピュータのハードウエア、ソフトウエアに関する知識、ネットワークのしくみ、セキュリティ、暗号などの専門的な知識を学ぶことができ、試験範囲を高いレベルでカバーしています。また、人工知能や統計、データサイエンスに関する科目も充実しており、G検定や統計検定などの受験に役立てることができます。さらに、本学のメディアセンターではWEB学習システムを通じて「ITパスポート試験 対策講座」と「基本情報技術者試験 対策講座」を無料で利用できる環境を提供しており、受験対策に活用することができます。 -
学園祭では研究発表を行うと先輩に聞きました。ユニークな研究内容をいくつか教えてください。
本学の学園祭である『目白祭』では毎年2・3年生が研究発表を行っています。2022年度は3年ぶりに目白祭が対面開催となり、学生たちが顔を合わせて準備をしたり来場者に直接説明をしたりする様子を見ることができました。2022年度のテーマは、「きれいな和音を作ろう」「パワーポイントでプロジェクションマッピング」「理論のり巻き」「最強のアニメキャラクターは?」「ドット&ボックス必勝法」「最速降下曲線とパスマスイッチ」「社会に役立つモバイルアプリケーション」「Proof of Workにおけるマイニングの実験」「p5jsで作るブロック崩しゲーム」「天体写真と画像処理」「重力加速度の測定」、など数学、物理学、情報科学に関連する多彩な発表がされました。
オンライン開催された2021年度の研究発表のテーマには以下のようなものがありました。
「数独と統計」「数学マジック」「写真からの立体復元」「一筆書きと曲率」「フレームワークを動かなくするパネルの張り方」「ぱすますいっち(からくりジェットコースター)」「ファッション評価AI」「子供見守りアプリ」「早押し判定機」「自作ドローン制御」「スマートフォン&PC連携Webプログラムについて」
これらの発表内容は以下のWEBページでも公開しています。ぜひご覧ください。
*数物情報科学科については学科ホームページもご覧ください。
化学生命科学科
-
学科の特色はなんですか?
1.化学と生物学、そして両者の複合領域も学べる
2.実験科目重視、幅広い分野の科目を選択できる
3.理系女性育成の伝統を受け継ぐ教育
4.教育設備の充実 -
他大学の理学部の化学科、生物学科との一番の違いは何ですか?
ほとんどの科目が選択科目であり、化学と生物学の幅広い分野の中から、自分の興味に合ったカリキュラムを組むことができます。化学と生物学の両方またはいずれかを中心とした時間割を作ることが可能です。また、複合領域である分子生命科学分野や環境科学分野の授業を加えることもできます。 -
バイオテクノロジーに興味があります。関連分野で現在どのような研究がされていますか?
多くの教員が、バイオテクノロジーの基礎となる遺伝子組換えや細胞培養などの技術を駆使した研究・教育に取り組んでいます。例えば、分子生物学を専門とする教員は、蛍光タンパク質を融合させたDNA複製因子の遺伝子をヒト培養細胞に導入して、DNAの複製機構に注目した研究に取り組んでいますし、遺伝学を専門とする教員は,動物の体色の進化に関して、遺伝子突然変異によって、色や模様を変化させたメダカを使って解析しています。また、遺伝子組換え植物を用いた学生実験も行われています。 -
生物の生態調査や野外での生物行動観察の授業・研究は行っていますか。
野外での植物観察・採集を行う実習や臨海実習があります。卒業研究では野外の観察・調査を取り入れた研究、森林のもつ環境浄化作用に関する研究も行われています。動物の生態調査や野外での行動観察の授業は行っていませんが、外部との共同研究は行っていますので、今後は卒業研究で扱う可能性があります。 -
将来、化粧品や食品の会社で働きたいのですが、化学生命科学科でそのための知識を学べますか?
そのような分野の基礎となる知識を学べます。化学、分子生命科学、生物学、環境科学の幅広い分野を履修可能なので、化粧品や食品会社で要求される広い基礎知識を学べます。また、学生実験で身につけた技術は、研究職についたときに役立ちます。 -
環境問題に関心がありますが、化学生命科学科で学べますか?
化学と生物学の両面から環境について学べます。例えば、「環境化学I,II」「環境生物学」「環境分析化学実験」「環境生物学実験」などの講義や学生実験があります。また、環境物質を対象にした分析化学、無機化学を研究している研究室もあります。また、環境汚染物質の生物分解に取り組んでいる研究室もあります。授業や卒業研究を通して環境分析の実験技術や解析方法などを身に付けることができます。 -
実験設備は充実していますか? 実験・演習の少人数とはどれ位でしょうか?
教育装置は充実しており、日本で最高水準を誇ります。1年次から分析機器を用いた実験を行い、3年次ではNMRやICP発光分析装置という、通常は研究用にしか使われない高価な装置を受講者全員が使用します。またデジタル画像解析装置を連結させた高度な生物顕微鏡システムを、1人1台の割合で1年次の学生実験から使用します。授業の実験は2~4名のグループに分かれ、1人1人が全てのテーマに参加しています。この他、2, 3年次には「化学生命科学英語」という少人数(10名内外)での英語論文の輪読の科目があります。 -
食品添加物や農薬など食品関係の実験・研究に興味があります。家政学部の食物学科と理学部の化学生命科学科では、どちらに進むべきでしょうか?
どちらの学科でも、実験・研究を行うことが可能ですし、どちらの学科の学生も食品関係の企業に就職しています。ただし大学で学ぶ内容には違いがあります。食物学科では、農学系の食品・栄養学、医学保健学、調理科学を柱とした食と健康に関する基礎知識を学ぶことができます。(食物学科のWebページ:「食物学科では、食を通して命を守り社会に貢献できる専門家の養成を目指し、食品学、栄養学、調理学、医学などの基礎的専門分野を修め、それらを生活に応用して発展させる力を養います。」)
化学生命科学科では、化学の基礎知識を活用しながら生物学を深く学ぶことも、化学の学習を中心としながら、生物学の素養を身につけることもできます。これによって、医薬、食品、農薬など幅広い分野で必要とされる基礎知識と技術を身につけるのみならず、専門分野の大学院への進学も可能です。こうした違いをよく考えて、進路を選択してください。 -
研究/技術職が希望なので大学院進学も考えています。研究/技術職への就職状況について教えてください。
大学卒であっても、研究/技術職(研究補助を含む)に就職される方が一定数います。企業によっては、技術系の採用に修士課程修了以上が要求される場合もあります。就職先としては、一般企業の他、大学や大学併設の研究所、国家公務員などがあります。本学科では、凸版印刷、日本食品分析センター、東芝などの研究/技術職で、多くの採用実績があります。 -
他大学の大学院へ進学する方は多いのですか?
卒業生の15~30%が毎年大学院に進学しています。2022年度の大学院進学者は33名でした。そのうち本学大学院への進学者が21名で、他大学の大学院へは、東北大学大学院、筑波大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、東京農工大学大学院、名古屋大学大学院、早稲田大学大学院に進学しています。 -
化学や生物の知識を生かせるような就職はできますか?
化学や生物の知識を生かせる分野は、食品、化粧品、製薬、醸造などがありますが、それらの知識が必要となる業種は製造業に限られません。従って、卒業生は、ソフトウェア開発なども含めた幅広い分野の会社に就職しています。たとえば、2022年度は、島津製作所(院卒)、Mizkan Holdings(院卒)、キリンビール、凸版印刷、岩城製薬、日本電気、農林水産省など、2021年度は、ポーラ、シミックファーマサイエンス、丸大ミート、大日本印刷、東京電力、ウェザーニュース、志賀国際特許事務所など、理系の知識を生かせる会社に毎年多数採用されています。 -
中学校・高等学校の「理科」教員免許を取得する学生はどのくらいいますか?また近年の採用状況を教えてください。
例年10名前後が免許を取得しています。その中には卒業と同時に専任教諭として採用される方もいます。2022年度は埼玉県公立中学校に、2021年度は横浜市公立中学校に採用されました。
*化学生命科学科についてはホームページが役に立つと思いますのでご覧下さい。
2023年7月更新












