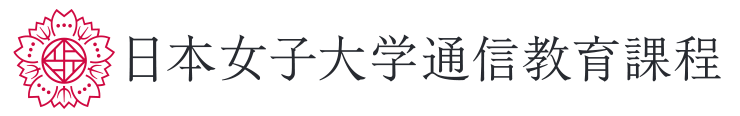学科科目
食物学科の科目は、食品学系、調理学系、栄養学系の3系列に分類され、他にこれらの系列の基礎となる基礎科目とその他の科目を置いています。
基礎科目
基礎化学I 基礎化学II 基礎分析学 生理学I 生理学II 食品・栄養学基礎実験I 食品・栄養学基礎実験II 微生物学 微生物学実験
食品学系
食生活と環境 食品学 食品化学 食品機能学 食品加工及び貯蔵学I 食品加工及び貯蔵学II 食品衛生学I 食品衛生学II 食品学実験 フードスペシャリスト論
調理学系
調理学 調理科学 フードコーデイネート論 調理学実習I 調理学実習II 調理科学実験
栄養学系
生化学I 生化学II 栄養学I 栄養学II 健康と栄養学I 健康と栄養学II 臨床栄養学I 臨床栄養学II 食教育論 基礎栄養学実習 応用栄養学実習 臨床栄養学実験
その他
食糧経済 家庭看護学 社会・環境と健康 健康科学と予防医学 病理学 解剖生理学 運動生理学 学校保健I 学校保健II 食品安全論 食物学特講II 地域食支援論 卒業論文
主な科目の紹介
食品・栄養学基礎実験II
基礎的な分析手法を学ぶ
本実験は、食品に関する種々の定量分析法の理論を理解し、これを実践することを目的としています。主要な食品成分(デンプン、たんぱく質、脂質)、水分、ビタミンCについて定量分析を行います。本実験で用いている分析方法は、食品成分表に記載されている成分量の算出法にほぼ準拠しています。従って履修により、世の中で実際に行われている分析手法を理解し、身につけることができます。
食品学
食品についての正しい知識・理解を
食品の情報は世の中に氾濫していますが、食品について正しく理解することは栄養摂取上、調理・加工上とても重要です。食品学では、食品の成分組成、理化学的性状、栄養特性、利用法など、基礎的なことを広く学び、正確な知識を得ることを目的としています。含有成分の特徴により食品を分類し、主要な食品を中心に学習します。さらに各々の食品の類似点、相違点についても理解を深めます。
調理学実習I・II
学んだ理論を、実習で体得していく
調理学では理論を勉強し、それを実際に体得するための実習です。調理学実習Iでは操作論の基礎を、調理学実習IIでは応用として和洋中の供応食を学びます。日本女子大学では、1901年の開校当初から実習教育を重視し、調理学実習を行なってきました。その伝統・文化を引き継いだ高度な調理を、現在の科学的理論の裏づけも含めた講義を交え、実演をします。その後、各グループに分かれ、個別に実習を行うことにより調理学を完結させます。
栄養学I
実際の食生活に直結した栄養学を
栄養の概念、食物の果たす役割を考え、食物から供給される各栄養素、すなわち炭水化物、脂質、たんぱく質、ミネラル、ビタミンおよび水について体内での機能を理解します。これらの栄養素は、生体の構成成分として代謝(利用)され異化されていきます。私たちの周囲にある食べ物を栄養学的見地からながめ、食べ物が健康維持・増進のために、いかに重要であるかを、実際の食生活に結びつけ把握し、栄養学の意義や使命を追究します。
社会・環境と健康
疾病予防のために生まれた学問
衛生学・公衆衛生学という社会医学の一分野を学びます。19世紀半ば、まだ細菌も発見されていない時代に、環境を改善すれば疾病は防げるという疾病予防のための疫学を主とした方法論として始められた学問領域です。現在でも疾病予防を主要な目標としています。集団、コミュニティを基本的な研究対象にし、保健統計、人口問題、環境問題、保健・医療・栄養・衛生行政、社会保障などについて広く学びます。本来は「健康科学と予防医学」とワンセットで学んでいただきたい科目です。
卒業要件
- 基礎科目
- 外国語:8単位
- 情報処理:2単位
- 身体運動:2単位
- 教養科目:24単位
- 学部共通科目:6単位
- 学科科目
- 卒業セミナー:2単位
- 自由選択科目:10単位
- 合計 124単位
卒業に必要な単位数のうち、修得が必要な最小スクーリング単位数
修業年限と在学しうる年数
- 1年次入学
- 修業年数(在学すべき年数)★:4年
- 在学しうる年数:10年
- 2年次編入学
- 修業年数(在学すべき年数)★:3年
- 在学しうる年数:8年
- 3年次学士入学
- 修業年数(在学すべき年数)★:2年
- 在学しうる年数:6年
卒業までにかかる年数は各自の状況により異なります。
人材養成・教育研究上の目的
『食物学科は、食品、栄養、調理を中心とした食と生活にかかわる諸科学を広く学び、食についての正しい科学的知識を修得し、その知識を生活および社会において人々の健全な食生活の推進と健康の増進のために活かして社会に貢献できる人材を養成することを目的とする。』
(日本女子大学人材養成・教育研究上の目的に関する規程より引用)
通信教育課程食物学科の3ポリシー
学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)
「教育目標・方針」
食に関する基礎科学的および専門的知識、技術を身につけ、食品関係の企業や教育の場や地域社会において貢献できる人材を育成する。食品学、調理学、栄養学に関する包括的な知識を身につけることができる。
- 〇食物学科DP1
食品、調理、栄養を中心とした食と生活に関わる諸科学を広く学び、科学的知識・専門的技術を修得できる。(大学DP1 大学DP2)
〇食物学科DP2
学修した食品、調理、栄養に関する科学的知識・専門的技術を用い、食に関する問題解決に応用することができる。(大学DP1 大学DP2)
〇食物学科DP3
食品、調理、栄養の視点から食物を総合的に理解するスペシャリストとして、他者と協働して様々な問題に取り組む姿勢が身につく。(大学DP1 大学DP3)
〇食物学科DP4
生活や社会といった観点から食に関する様々な課題を見つけ、正しい科学的知識に基づいて解決方法を論理的に洞察し、プレゼンテーションすることができる。(大学DP2 大学DP3)
〇食物学科DP5
生活や社会に及ぼす食の影響や効果を生涯学び続け、食に関する様々な問題の解決に努めようとする積極的な姿勢が身につく。(大学DP3 大学DP5)
〇食物学科DP6
人々の健全な食生活の推進と健康の維持増進のために社会に貢献し、食に関する諸問題に地球環境・SDGsを考えてグローバルな視点から取り組む態度が身につく。(大学DP4 大学DP5)
教育課程編成方針(カリキュラム・ポリシー)
【教育課程・教育方法】
食物学科では、「生活者」の視点から食を科学するのに必要な内容として、主に1年次に自然科学系基礎科目群および導入的内容の専門科目群(基礎・導入科目)、2年~3年次に発展的内容の専門科目というカリキュラム構成になっている。基幹となる専門科目群は「食品学系」「調理学系」「栄養学系」に大別され、それぞれテキスト科目、実験実習の順に開講されており、理論を実際の作業で確認できるように配置されている。
Learning Management System: manabaやTeamsを積極的に活用し、テキスト科目、演習科目、実験・実習科目において、積極的にアクティブ・ラーニングが用いられ、いずれの科目においても論理的思考力、コミュニケーションスキルやプレゼンテーション力が身につく。
- 「基礎科学系」および導入的内容の専門科目
専門科目の理解に必要な「化学」、「生物学」に関する発展的な内容を学ぶテキスト科目、スクーリングでの講義科目、実験科目を置く。
「食品学系」
基幹となる専門科目群の一つ。様々な食品の成分とそれらの機能性・食品の加工貯蔵・食品衛生を学ぶテキスト科目、スクーリングでの講義科目、スクーリングでの実験科目を置く。
「調理学系」
基幹となる専門科目群の一つ。高度な調理技術、調理加工食品の「物性」や「おいしさ」に対する解析能力・評価方法を学ぶテキスト科目とスクーリングでの実験・実習科目を置く。
「栄養学系」
基幹となる専門科目群の一つ。健康な食生活を通した生涯の健康の保持・増進を学ぶテキスト科目とスクーリングでの実験・実習科目を置く。
「卒業論文」
4年間の学修の集大成として、卒業研究を希望する学生のために、選択科目として卒業論文を配置する。
専門科目に加え、教職課程の履修により、家庭科の中学校・高等学校教諭一種免許が取得可能である。また、フードスペシャリスト関連科目の履修により、フードスペシャリスト、専門フードスペシャリスト資格を取得することができる。
【学修成果達成のための科目】
- 〇食物学科DP1
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」
〇食物学科DP2
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」「卒業研究」
〇食物学科DP3
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」
〇食物学科DP4
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」
〇食物学科DP5
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」「卒業研究」
〇食物学科DP6
「基礎科学系」「食品学系」「調理学系」「栄養学系」
取得できる資格
- 中学校・高等学校教諭一種免許状(保健)
- 中学校・高等学校教諭一種免許状(家庭)
- 学校図書館司書教諭
- フードスペシャリスト(受験資格)
- 食物学科ではフードスペシャリスト資格を取得可能です。この資格は、食に関する総合的・包括的な知識と技術を持ち、食品の製造、流通、消費の分野で活躍することのできる食のスペシャリストに与えられる資格です。具体的な仕事は、新商品の開発、品質管理、流通管理、広報活動、商品企画、販促企画、消費者対応、レストランでのメニュー開発、食空間の演出などがあります。消費の下流から食品産業を見て、問題点を改善し消費者が求める食生活の実現のために働く仕事をします。
教員からのメッセージ
食物学科で学ぶ科目は、食品学、調理学、栄養学の3分野に大きく分けられます。基礎から学び、総合的な知識を身につけ、食をめぐる様々な問題に対処し社会貢献できるようになることを目指します。通信教育での学習では、目標を決めて着実にこなしていくことが大切になります。生活のスタイルに合わせて、無理のないペースで進めていってください。学習していて疑問が生じたときには、質問票を活用されるとよいと思います。
教員紹介