コンテンツ
2025/10/31
- 校長より
「読書のすゝめ」(2025/10/31)
日本初の女性の内閣総理大臣が誕生しました。昨年、メキシコ史上初の女性大統領にシェインバウム氏が就任した時、新聞委員会の生徒が生徒会の機関紙「われら」に、「女子のみで運営・実施する本校の自治」と絡めながら記事を書きました。今年はどのような意見が飛び交うか、とても楽しみです。
中学2年生は9月、10月の授業で『アンネの日記』を学びました。アンネは日記の中で次のように述べています。
「うちのおかあさんや、ファン・ダーンおばさんや、その他大勢の女性たちのように、毎日ただ家事をこなすだけで、やがて忘れられてゆくような生涯を送るなんて、わたしには考えられないことですから。わたしはぜひともなにかを得たい。夫や子供たちのほかに、この一身をささげても悔いないようななにかを」「わたしは世間の大多数の人たちのように、ただ無目的に、惰性で生きたくはありません。周囲のみんなの役に立つ、あるいはみんなに喜びを与える存在でありたいのです」(文春文庫 深町眞理子訳)。何を自分の目的として生きるか、それは人によって様々だと思います。男女を問わず、家庭の中でじっくりと家事や子育てをするのが喜びという人もいれば、自分の得意なことを生かして社会でバリバリ働きたいという人もいます。それでもアンネの言うように「周囲の人の役に立ったり、喜びを与える存在でありたい」と考えることはとても大事だと思うのです。生徒たちには、自分の事だけにとらわれるのではなく社会のために動くことも視野に入れて、将来を展望してほしいと願っています。
清少納言は『枕草子』の「生ひさきなく、まめやかに、えせざいはひなど見てゐたらむ人は、いぶせくあなづらはしく思ひやられて…」という文章で「これといった将来の見込みもなく、ただまじめに、いいかげんな幸福などを本物の幸福と見て暮らしているような人は、私にとっては、うっとうしく軽蔑すべき人のように思われて、やはり、相当な身分の人の娘などは、人の仲間入りをさせて、世間のありさまも見せて慣れさせたく、内侍のすけなどで、しばらくお仕えをさせておきたいものだと感じられる」(22段 小学館 日本古典文学全集)と書いています。かなり激しい物言いですが、社会に触れてこそ視野が広がり、考え方も深まると考えているところはさすがです。
1000年以上前に感性豊かな筆致で『枕草子』を書いた清少納言も、90年近く前に「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」と日記で自己の思いを綴ったアンネ・フランクも、書いたものが残っているからこそ人柄が伝わってきて、それを読む私たちも様々に考えることができるのです。書いたものは時代も国も超えて、私たちの心を揺さぶります。秋の夜長にぜひ本を読んで、自分の心を育てていけたらよいと思います。
-
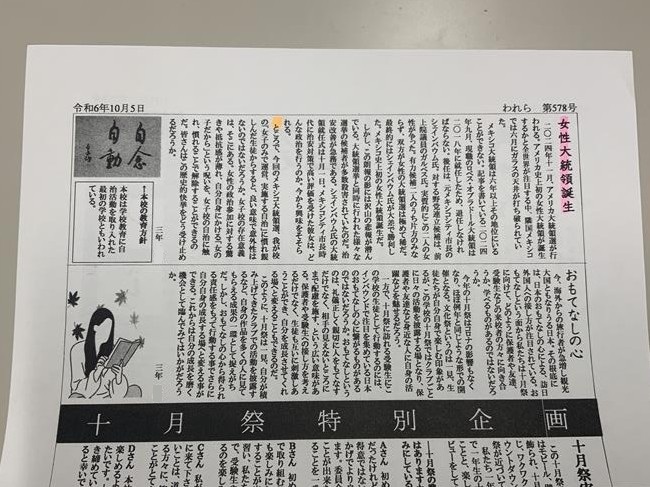
機関誌「われら」第578号(令和6年10月5日発行) -
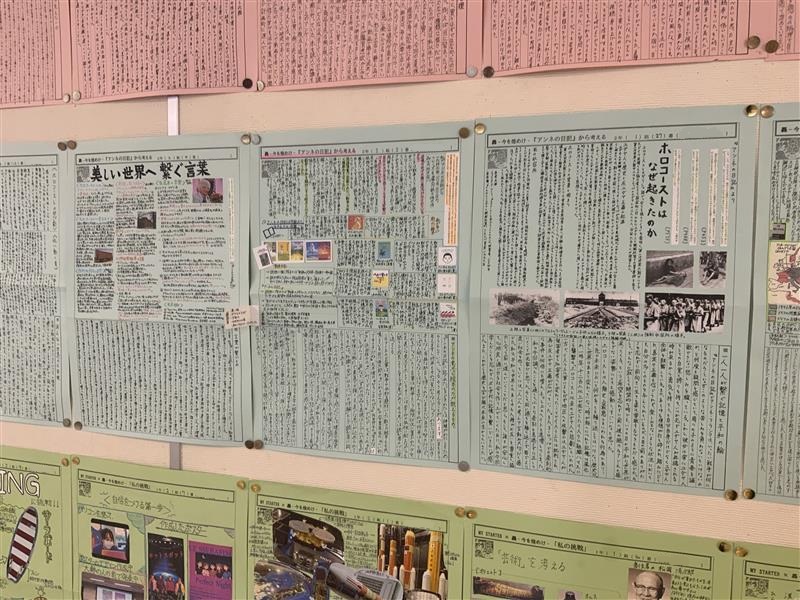
2年生 夏休み課題「アンネの日記から考える」 -

来週から始まる読書会に向けて準備を進めています


