コンテンツ
2020/05/21
- 教員リレーエッセイ
【5月】「距離」を意識する日々
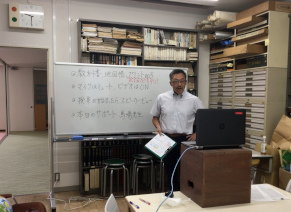
コロナ禍のなか、「距離」を意識する日々が続いています。
私は、授業で「距離」について話すことがあります。生徒に「中学校は、駅からどれくらい離れている?」と問いかけると、「徒歩10分」「私、15分」「それ、ゆっくり歩きすぎ」なんて声があがります。このように、私たちは日常生活で「どれほど離れているか」を表現するのに、距離を表す単位(km,m)をあまり用いません。私たちが普段、意識するのは「空間的な距離」でなく、その場所に行くためにかかる「時間」「費用」「労力(手間)」という「時間的な距離」や「経済的な距離」なのです。(授業ではこの後「交通の便を改善する」とはどういうことかという内容に進みます。)
ところが今、私たちは日ごろ注目度が低い「空間的な距離」について、とても考えています。感染を防ぐための距離とは、自宅にいる生徒との距離を埋める方法とは、日々「距離」のことが頭から離れません。距離を保つことを心掛けてみると、実現が困難な状況もありました。普段、この中で生活していたのかと嘆息する一方で、今、身の回りにある「空間的な余裕」とは心地よいものだということを再認識しました。旅先の広い客室や露天風呂で味わう感覚に似ていると言ったら、言いすぎでしょうか。
また、生徒たちとオンラインの授業やHRでつながっていると、「空間的な距離」を解消してくれるインターネットの可能性と限界を肌感覚で捉えられます。慣れないオンライン授業を手探りで進めていくのは正直たいへんです。でも、インターネットがない状況を今は想像したくありません。一方、オンラインでのつながりに、直接会うことで得られる何かが欠けていることは、皆さんが感じていることでしょう。
そして、「早く学校に行ってみんなと話したい」と言う生徒たちと向き合うなかで感じたことがあります。インターネットの使い方には2種類あると。
「直接会って話したいけど、(それは困難なので)代わりにインターネットでつながる」
「直接会って話すことより、(いろいろな意味で)インターネットでつながる方が便利」
前者が、もともとインターネットが生まれた理由のように思います。そして、今、前者の理由でインターネットをフル活用しています。私たちは、日常生活のなかで、極めてあたりまえに後者の使い方をしてきましたし、それがスタンダードだと思います。しかし、今の非日常が気づかせてくれた「やはり直接会って話すことに勝るものはない」ということを、コロナ後の生活のなかでも忘れないようにしたいと思います。


